


|
宿泊先から地下鉄にて、とりあえずナショナルレイルのWATERLOO駅へ向かいます。
|


|
地上に出てナショナルレイルに乗り換えです。耳慣れた地名として途中、ウィンブルドンを通過するようです。
|

|
そう遠くに行くわけではありませんので、やはり毎回乗車ホームが決まっていないのは、日本の感覚で思うと少々面倒です。 |

|
この路線に乗るのは今回が初めてですが、後にウィンブルドン周辺の楽器店に行く事となり乗る機会が在りました。
|




|
サービトン駅、乗ってしまえば確かに近いです。20分もかかりませんでした。
東海道線、横浜~品川間という感じでしょうか。 |


|
駅を出たところで、右方向へ歩きます。 |


|
通りすがりの教会と時計塔。 |


|
Y様宅に着きました。
正に引越しのお忙しい中お邪魔させて頂きました。
日本人なら誰でも知っている大手の運送会社さんが来ておりました、作業員(日本人)の方にお話を伺った所、日本人宅の仕事だけで1年中あるとの事で、驚きです。。
|




|
今回連絡を頂きましたY様より、入手の経緯や現地の調律師による話、使用状況などを伺いました。
次に、実際に現物を見せていただきましたところ、画像で見たようにアンティーク感たっぷりの、とっても素敵な外観でした。
全く同じものは日本では無いであろうと思われ、持ち帰りたくなる気持ちはとても分かるものです。
燭台は年代的に後付であろうと思いますが、いろいろと考えていくと三つ窓のモールも後付の可能性が出てきます。
|



|
次に、Y様にお調べいただいたブランド名です。
当社にてアメリカ製の古いピアノを扱った経験は少ないものですが、ざっと目を通した感じで、ヨーロッパ製(ドイツ、イギリス製)ではないのか?と思われるものでした。
鍵盤蓋の内側、REINHARDと貼られていますが、後から貼った長方形の突き板の上からですので不自然です。
また、ロゴの字体が時代的に地味で、ここでも少々??となります。
20世紀初頭まではブランド名の下に
Berlin,Leipzing,Paris,London などと都市名も入っていることが多く、それが無い場合はフレームにあるのが普通ですが、そこにも見当たりません。
また、フレーム上のロゴは手書きだけなためにどうにでも出来てしまいます。蓋の突き板を剥がすと下からオリジナルロゴが出てくるのではないかと思われます。
ただこの推測が当たっていたとしても、なぜ名前を変えたのかは全く分かりません。 |

|
次に構造的な面と内部の状態を見て行きます。 |

|
1900年前後はモダンピアノの過渡期にあたり進歩の度合いがメーカーにより違い、オーバーダンパーアクションやフレームが上部までフルに来ていない物なども在り様々です。
|

|
このピアノは既にそれらの進化は遂げていて旧式と言えるのは唯一響板が左右方向へ貼られている事です。
アクションと鍵盤(85key)の構造に関しては9割方が現在と同様です。
こうして見ると外観のアンティークな様相より実際はもう少し若く1920年以降の製造ではないかと思われます。
この1920年を過ぎて(第一次大戦以降)からアクション構造、外観を含め現代のピアノにかなり近くなりここにも一つの境が在ります。
|




|
まず根幹部分のフレーム、チュウニングピン板(英名 Wrest Plank)、響板関係と見て行きます。
ピン板の小さな亀裂と低音部分のピンホールの広がりと言った劣化が直ぐに目に付きチュウニングハンマーにてチュウニングピンを廻した所やはり緩くY様が仰っていた「調律が狂う」の大方の原因がこれに当ります。
このピアノはピン板(木部)とフレーム(金属)が同色に塗装されている為に一見境が分かりずらい物ですがピンが刺さっている垂直面が
木部(ピン板)となりそれを囲っている枠だけが金属(フレーム)となります。
このピン板への長年下方向からの弦張力に木が絶えられなくなって問題が起こります。
主に低音セクションに症状が出ていますがグランド、アップライト、メーカー問わずこの箇所から始めに劣化(緩み)が起こりますので今回もその例に漏れない事と言えます。
この板に掛かる負担を減らす為か後にこの部分を全てフレームで被って弦張力をそれが支える構造に変わって行ったメーカーも多々在ります、ただ同じ構造にて最近まで製造した有名なメーカーも在り設計思想の違いと言う事だと思います。
尚、このピン板の剥き出し構造をイギリスで Open Plank と言っています。
(フレーム構造、アクション関係、下記参考資料在り)
|

|
フレーム
やはり弦張力の掛かる部分へ割れ(クラック)が生じている事が在りますが問題在りませんでした。
|



|
響板関係、画像の様、横方向に隙間が出来てます、この場合は製造時に継いだ(接着した)箇所が板の収縮により開いた物です、その為に隙間が一直線です。
板そのものが割れて(裂けて)いる場合もありますがその場合には木の目に沿って割れが走るので完全に直線と言う訳では在りません。
今回の場合にはその木の縮みによる接着の剥がれです、総称としては「響板割れ」と言ってます。 |

|
裏側は見ていませんが響板を貼り繋いでいる響棒は通常響板に対して直角方向へ貼られている為このピアノもそのはずです。
駒の方は亀裂や剥がれなど見当たりませんでした。
|
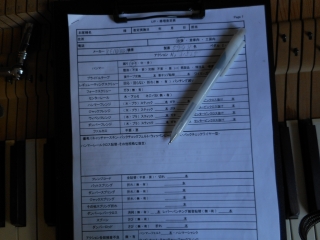
|
他の箇所も目を通し一応後の事を考え記録を取っておきます。 |

|
チュウニングピン付近にやたらと液体物が付着してますが故意に付けた(塗った)様です、緩くなったチュウニングピンを硬くする為、ピン板のホールへ染込ませる液体が売られてはいますがその類なのかちょと何とも言えません。
|


|
鍵盤関係のチェックです、白鍵に剥がれが生じていましたが単純に接着すれば問題ないはずです。
Y様から象牙白鍵と聞いていましたがセルロイド製でしたアイボリー色の為にその様に思われたのだと思います。
ただこれもオリジナルなのか定かでは在りません、修理の際に象牙からその様に張替えられたピアノもよく見かけます。
|
余談ですがY様は準備が良くご自分で象牙鍵盤としての輸出許可(サイテス)を英国政府から撮られていました、現物チェックをする訳ではないので、申請すれば何でも(セルロイドでも)通ってしまう様です。。
私は以前パリで仕入れた象牙鍵盤のピアノをロンドンに運び英国政府発行のサイテスにより日本に送った事が有りましたがその条約内容等未だによく分からない部分が多々在ります。
|

|
木製センターレールが少々割れています。 |


|
このピアノは過去に修理が入っている事も在りフレーム、響板に比べると鍵盤、アクション関係の状態が良くハンマーは特に綺麗な為、過去にフェルト張替え(交換では無く)をした可能性も考えられます。
|

|
低音部以外も一通りチュウニングピンの硬さを確かめておきます。
|
これで背面以外は一通り目を通しました、今回の一番大きなダメージとしてはチュウニングピン板の劣化と言う事となります。
現在のピアノとはまた一味違う良い音を発している物ですが調律が直ぐに狂いを生じてしまうのでは困ります。簡易修理にて調律を出来る様にすればしばらくは使えるはずです、長期的に考えるとピン板自体の交換が必要で、この場合はフレームを外す為、通常は同時に響板補修や弦張替えも伴い、費用と期間は掛かる事となります。
アクションと鍵盤関係は現在とほぼ同構造な為にきちんと調整すれば弾きやすくなる物です。
一応この時点で分かる範囲をY様へお話し、詳しくは後にまたたメールでお伝えする事としました。 |

|
帰途にて。 |


|
まだ陽は落ちてませんが本日はこの後に仕事は無い為、サービトン駅前のパブにてユニオンジャックを背にギネスビールで一人慰労会としました。
|
|
将来もしピアノを直される際にはご相談お待ちしております、
この度はご協力誠に有難うございました。
Y様はその後、ピアノを日本に持ち帰られました。
(有)クラビアハウス 代表 松木一高
(* 上記、Y様ご了解の上で掲載させて頂いております。)
|